寿司図鑑 619貫目
寿司図鑑1~856貫目は旧コンテンツからの移行データの為、小さい写真の記事が多くあります。
寿司図鑑1~856貫目は旧コンテンツからの移行データの為、小さい写真の記事が多くあります。
大鳥貝/オオトリガイ
おおとりがい /


握り Nigiri軍艦巻 gunkanmaki海苔巻 Norimaki丼・ちらし Don/Chirashi郷土ずし Kyoudozushiなれずし Narezushiいずし Izushiいなりずし Inarizushiその他 Others
貝類学者にとってオオトリガイはそんなに珍しい貝でもない。
ありふれていて、貝殻自体も美しくないので“気にもとめない”という存在のようだ。
底引き網のゴミの中によく、この大型の天保通寶のような貝殻を見る。
浅場の砂泥地にはかなりいるのではないだろうか?
愛知県一色などでは少ないが生きているものもあがる。
しかし、そんな軟体入りのものを見たのは一、二回でしかない。
それが目の前にごっそりときた。
驚いたことに、かなりグロテスクな生き物で、生きが良く海水をドロドロと吐き出している。
岡山県倉敷市児島高洲でとれたもの。
姫路のダイスケさんがとったものを送ってくれたのだ。
高洲というのは全国的にも珍しい多種多様な貝類がとれる潮干狩り場。
アサリをとるとか、シオフキをとるなんて平凡なことはしない。
ここでの獲物は、それこそタイラギ、ナミガイ、アカマテガイなど大小入り交じる。
またこのいろんな貝をとるすべは、総てお客の側が開拓していったというのも面白い。
だからタイラギひとつとっても、よそ者が勇んで高洲に行ったからといってとれるわけじゃない。
そこには並み居るプロ達がいる。
例えばナミガイのプロといったら倉敷市の陶芸家武内立爾さんにかなう人は少ない。
タイラギ、アカマテガイなど目差す貝毎にその道の玄人がいるのだ。
すなわち高洲には貝毎に取り方を開拓した名人がいるのだ。
オオトリガイの取り方の開拓者はダイスケさんであり、今のところ追随者はいないという。
食の上でも国内においてはオオトリガイを食べている人は皆無だと思う。
貝類の専門家に言わせると東南アジアに行けば普通に市場に並んでいるという。
さて、この大型の貝をどう仕込んだらいいのだろう。
軟体を貝殻から外すのが先決だ。
かなり軟らかな軟体で、水管をベール状の皮膜がおおっている。
二枚貝の前方に当たる部分には大きな足もある。
ちょっと不気味な斑模様の水管、足を二つ割にして、湯通しする。
北帰貝(ウバガイ)と同じ仕込み方だ。

●クリックすると拡大
ボクの仕込んだネタを見て、たかさんがまず口を開く。
「水管の切り付けが難しいね。形にならないよ」
まな板の前で、本当に柳包丁をかまえたまま、たかさんは止まってしまっている。
「本邦初めての握りだから、あんまり形は気にしなくていいよ」
「そうはいかないよ」
ままよ、と握り始めるとあっというまだ。
「やっぱり水管の赤い斑点が不気味だね」
たかさんは一かん口に放り込みながら呟く。
「でもうまいね。みる(ミルクイ)と比べると味が薄いけど、甘味があっていいね。難点は軟らかいことかな。ああ、それと(この貝独特の)個性がないかな」
ボクには甘味も旨味も平凡だし、食感もイマイチに思える。
寿司ネタとして出てきたら、それなりにイケルのかも知れないが本みる(ミルクイ)、白みる(ナミガイ)よりは劣るようだ。
帰宅して、水管、足以外の部分をササーとバター焼きにしてみた。
炒めてみると、予想外にうまい。
東南アジアではどのように食べられているのだろう。
ダイスケさんに感謝いたします。
2008年5月15日のメモから
倉敷市児島高洲の「からこと丸」へ
http://www.tamano.or.jp/usr/karakoto/index1.html
ありふれていて、貝殻自体も美しくないので“気にもとめない”という存在のようだ。
底引き網のゴミの中によく、この大型の天保通寶のような貝殻を見る。
浅場の砂泥地にはかなりいるのではないだろうか?
愛知県一色などでは少ないが生きているものもあがる。
しかし、そんな軟体入りのものを見たのは一、二回でしかない。
それが目の前にごっそりときた。
驚いたことに、かなりグロテスクな生き物で、生きが良く海水をドロドロと吐き出している。
岡山県倉敷市児島高洲でとれたもの。
姫路のダイスケさんがとったものを送ってくれたのだ。
高洲というのは全国的にも珍しい多種多様な貝類がとれる潮干狩り場。
アサリをとるとか、シオフキをとるなんて平凡なことはしない。
ここでの獲物は、それこそタイラギ、ナミガイ、アカマテガイなど大小入り交じる。
またこのいろんな貝をとるすべは、総てお客の側が開拓していったというのも面白い。
だからタイラギひとつとっても、よそ者が勇んで高洲に行ったからといってとれるわけじゃない。
そこには並み居るプロ達がいる。
例えばナミガイのプロといったら倉敷市の陶芸家武内立爾さんにかなう人は少ない。
タイラギ、アカマテガイなど目差す貝毎にその道の玄人がいるのだ。
すなわち高洲には貝毎に取り方を開拓した名人がいるのだ。
オオトリガイの取り方の開拓者はダイスケさんであり、今のところ追随者はいないという。
食の上でも国内においてはオオトリガイを食べている人は皆無だと思う。
貝類の専門家に言わせると東南アジアに行けば普通に市場に並んでいるという。
さて、この大型の貝をどう仕込んだらいいのだろう。
軟体を貝殻から外すのが先決だ。
かなり軟らかな軟体で、水管をベール状の皮膜がおおっている。
二枚貝の前方に当たる部分には大きな足もある。
ちょっと不気味な斑模様の水管、足を二つ割にして、湯通しする。
北帰貝(ウバガイ)と同じ仕込み方だ。

●クリックすると拡大
ボクの仕込んだネタを見て、たかさんがまず口を開く。
「水管の切り付けが難しいね。形にならないよ」
まな板の前で、本当に柳包丁をかまえたまま、たかさんは止まってしまっている。
「本邦初めての握りだから、あんまり形は気にしなくていいよ」
「そうはいかないよ」
ままよ、と握り始めるとあっというまだ。
「やっぱり水管の赤い斑点が不気味だね」
たかさんは一かん口に放り込みながら呟く。
「でもうまいね。みる(ミルクイ)と比べると味が薄いけど、甘味があっていいね。難点は軟らかいことかな。ああ、それと(この貝独特の)個性がないかな」
ボクには甘味も旨味も平凡だし、食感もイマイチに思える。
寿司ネタとして出てきたら、それなりにイケルのかも知れないが本みる(ミルクイ)、白みる(ナミガイ)よりは劣るようだ。
帰宅して、水管、足以外の部分をササーとバター焼きにしてみた。
炒めてみると、予想外にうまい。
東南アジアではどのように食べられているのだろう。
ダイスケさんに感謝いたします。
2008年5月15日のメモから
倉敷市児島高洲の「からこと丸」へ
http://www.tamano.or.jp/usr/karakoto/index1.html
寿司ネタ(made of)
オオトリガイ
ー
銚子以南、京都府宮津市阿蘇海、九州。
臺灣(台湾)、東南アジア。・・・・
市場魚貝類図鑑で続きを読む⇒
この寿司ネタの他の寿司(Others)
- 登録がありませんでした

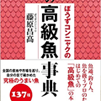 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典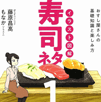 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生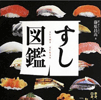 すし図鑑
すし図鑑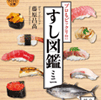 すし図鑑ミニ
すし図鑑ミニ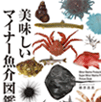 美味しいマイナー魚介図鑑
美味しいマイナー魚介図鑑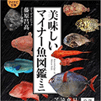 美味しいマイナー魚図鑑ミニ
美味しいマイナー魚図鑑ミニ ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー!
ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー! からだにおいしい魚の便利帳
からだにおいしい魚の便利帳 地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻
地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻