寿司図鑑 618貫目
寿司図鑑1~856貫目は旧コンテンツからの移行データの為、小さい写真の記事が多くあります。
寿司図鑑1~856貫目は旧コンテンツからの移行データの為、小さい写真の記事が多くあります。
名残の麦烏賊で作る煮いか
なごりのむぎいかでつくるにいか /


握り Nigiri軍艦巻 gunkanmaki海苔巻 Norimaki丼・ちらし Don/Chirashi郷土ずし Kyoudozushiなれずし Narezushiいずし Izushiいなりずし Inarizushiその他 Others
関東ではスルメイカの小振りのものを「麦いか」と呼ぶ。
これは麦の刈り取り時期がスルメイカの子供のとれ盛る時期と同じであるからだ。
麦の収穫時期がとっくに終わった八月になっても「麦いか」は徐々に入荷量を減じながらやってくる。
今回のものは仲卸のミノルちゃんが「銚子じゃないの」というけど産地不明である。
この遅い時期のスルメイカの子供は太平洋を北上する「冬生まれ群」。
銚子産といわれてもそんなに外れているわけではないだろう。
関東に小振りのスルメイカが入荷してくるのが真冬から八月くらいまで。
これをササーと煮て、握りずしのネタとするのだけど、これがまことに味わい深いもの。
さて市場で買い求めたら、その場でまな板を借りて胴からゲソを抜き取り、ワタを捨て去る。
「ワタを捨てるなんてもったいない」
そんな声が聞かれそうだが、必要なときには持ち帰ればいいし、使わなければ捨てればいい。
ときどき「スルメイカはワタが命」とか「サンマのうまさはワタにあり」なんてことを言うバカがいるが、魚はどのようにして食べたいのか、そのときワタがいるのか? いらないのか? 臨機応変に致すのが料理なのだ。
ボクはこのような通り一辺倒な、わかりやすいことを言うヤカラに嫌悪感を持つ。
さて、きれいに胴のなかを洗い、持ち帰ったら、できるだけていねいに水分を拭き取る。
鍋に酒、醤油、砂糖、水の地を味見しながら仕立てる。
地が沸き上がったら、ここに一つずつスルメの胴を放り込んで鍋の中でクルクル回し、胴の中に箸を突っ込んで、胴の中にも地が回り込むようにする。
地の味加減はお好きなようにやってほしい。
今回は寿司ネタなので味は控えめに。
数十秒で煮上がるので、バットなどに上げる。
冷えたらビニール袋に放り込み、ほんの少し煮汁を加える。
袋の中に少しだけ煮汁を入れるだけで「煮いか」が乾かなくて済む。
寿司ネタなら決して煮汁に漬け込むなんてことをやってはいけない。
「煮いか」を作るのが目的で、例えば酒の肴やおかずにするなら、煮汁に鍋止めをしてもよい。

●クリックすると拡大
これを行きつけの店。
ようするに『市場寿司 たか』で握ってもらう。
今回のは「麦いか」といってもやや大振りなので一本で七、八かんも切り付けられそうである。
さて、たまたま居合わせた島根県松江市在住のヤマトシジミさんにも加わってもらって、「煮いか」の握りを食らう。
見た目は決してよいわけではない。
どちらかというと鄙びたものである。
たかさんと、ボクは1シーズンに何度も食べる煮いか。
今回『寿司図鑑』作成に急遽加わってもらったヤマトシジミさんにも喜んでいただけたようだ。
「軟らかいでしょう」
「いいですね。こう言うのも」
「東京の寿司屋では定番的なものなんです。また握りのネタはあまりうますぎてもいけないんで、やや控えめに味付けしてます」
さて、どうしてついつい「煮いか」を作ってしまうのか?
それは「煮いかの握り」が大好きだからだ。
スルメイカの皮目の風味、そして甘味、独特の旨味。
軟らかく仕上げているので、寿司飯との相性もいい。
「たかさん、今度は大型のスルメで煮いかを作るからね」
「ああ、待ってるよ。オレは大きい方が好きだよ」
さて秋に大スルメが出始めたら、真っ先に「煮いか」を作らなければ!
これは麦の刈り取り時期がスルメイカの子供のとれ盛る時期と同じであるからだ。
麦の収穫時期がとっくに終わった八月になっても「麦いか」は徐々に入荷量を減じながらやってくる。
今回のものは仲卸のミノルちゃんが「銚子じゃないの」というけど産地不明である。
この遅い時期のスルメイカの子供は太平洋を北上する「冬生まれ群」。
銚子産といわれてもそんなに外れているわけではないだろう。
関東に小振りのスルメイカが入荷してくるのが真冬から八月くらいまで。
これをササーと煮て、握りずしのネタとするのだけど、これがまことに味わい深いもの。
さて市場で買い求めたら、その場でまな板を借りて胴からゲソを抜き取り、ワタを捨て去る。
「ワタを捨てるなんてもったいない」
そんな声が聞かれそうだが、必要なときには持ち帰ればいいし、使わなければ捨てればいい。
ときどき「スルメイカはワタが命」とか「サンマのうまさはワタにあり」なんてことを言うバカがいるが、魚はどのようにして食べたいのか、そのときワタがいるのか? いらないのか? 臨機応変に致すのが料理なのだ。
ボクはこのような通り一辺倒な、わかりやすいことを言うヤカラに嫌悪感を持つ。
さて、きれいに胴のなかを洗い、持ち帰ったら、できるだけていねいに水分を拭き取る。
鍋に酒、醤油、砂糖、水の地を味見しながら仕立てる。
地が沸き上がったら、ここに一つずつスルメの胴を放り込んで鍋の中でクルクル回し、胴の中に箸を突っ込んで、胴の中にも地が回り込むようにする。
地の味加減はお好きなようにやってほしい。
今回は寿司ネタなので味は控えめに。
数十秒で煮上がるので、バットなどに上げる。
冷えたらビニール袋に放り込み、ほんの少し煮汁を加える。
袋の中に少しだけ煮汁を入れるだけで「煮いか」が乾かなくて済む。
寿司ネタなら決して煮汁に漬け込むなんてことをやってはいけない。
「煮いか」を作るのが目的で、例えば酒の肴やおかずにするなら、煮汁に鍋止めをしてもよい。

●クリックすると拡大
これを行きつけの店。
ようするに『市場寿司 たか』で握ってもらう。
今回のは「麦いか」といってもやや大振りなので一本で七、八かんも切り付けられそうである。
さて、たまたま居合わせた島根県松江市在住のヤマトシジミさんにも加わってもらって、「煮いか」の握りを食らう。
見た目は決してよいわけではない。
どちらかというと鄙びたものである。
たかさんと、ボクは1シーズンに何度も食べる煮いか。
今回『寿司図鑑』作成に急遽加わってもらったヤマトシジミさんにも喜んでいただけたようだ。
「軟らかいでしょう」
「いいですね。こう言うのも」
「東京の寿司屋では定番的なものなんです。また握りのネタはあまりうますぎてもいけないんで、やや控えめに味付けしてます」
さて、どうしてついつい「煮いか」を作ってしまうのか?
それは「煮いかの握り」が大好きだからだ。
スルメイカの皮目の風味、そして甘味、独特の旨味。
軟らかく仕上げているので、寿司飯との相性もいい。
「たかさん、今度は大型のスルメで煮いかを作るからね」
「ああ、待ってるよ。オレは大きい方が好きだよ」
さて秋に大スルメが出始めたら、真っ先に「煮いか」を作らなければ!
寿司ネタ(made of)
スルメイカ
Japanese flying squid
市場魚貝類図鑑で続きを読む⇒

 スルメイカ稚イカ生軍艦巻き
スルメイカ稚イカ生軍艦巻き スルメイカ稚イカ釜揚げ
スルメイカ稚イカ釜揚げ スルメイカの煮いか
スルメイカの煮いか いかの樽寿司
いかの樽寿司 いかずし
いかずし スルメイカの握り
スルメイカの握り 野菜入いかずし
野菜入いかずし スルメイカ
スルメイカ 煮いか/スルメイカ
煮いか/スルメイカ 麦いか握り
麦いか握り ばら烏賊の煮イカ
ばら烏賊の煮イカ 青森県むつ市いかずし
青森県むつ市いかずし いかずし
いかずし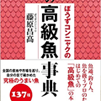 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典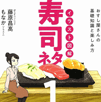 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生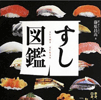 すし図鑑
すし図鑑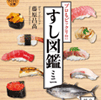 すし図鑑ミニ
すし図鑑ミニ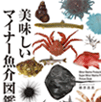 美味しいマイナー魚介図鑑
美味しいマイナー魚介図鑑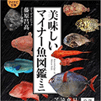 美味しいマイナー魚図鑑ミニ
美味しいマイナー魚図鑑ミニ ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー!
ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー! からだにおいしい魚の便利帳
からだにおいしい魚の便利帳 地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻
地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻