寿司図鑑 1472貫目
かんぴょう巻き
かんぴょうまき /


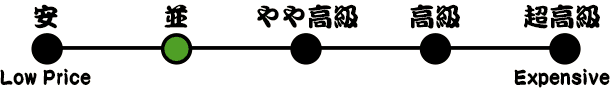
握り nigiri軍艦巻 gunkanmaki海苔巻 Norimaki丼・ちらし Don/Chirashi郷土ずし Kyoudozushiなれずし Narezushiいずし Izushiいなりずし Inarizushiその他 Others
干瓢(かんぴょう ユウガオ)は室町時代には栽培されていたともされている。国内最初の産地は大阪市木津で、それが滋賀県水口が産地になり、この水口藩主であった加藤氏が元禄期に下野国壬生藩に国替わりしたときに干瓢の栽培法を持ち込んだとされている。
下野の国(栃木県)で栽培し、加工された干瓢は江戸の町に来て、巻きずしなどに欠かせないネタとなっている。
すし職人として最初に習うのも干瓢の仕込み方であるとも。
干瓢はぬるま湯で戻し、塩もみして水洗いする。これを砂糖、しょうゆで煮て、仕上げにみりんを振る。みりんを入れないという職人もいる。
今回のものは砂糖としょうゆ、少量の酒で煮て、仕上げに少量のみりんを振ったもの。やや甘味がちな味が巻きずしには合う。
近年、干瓢を煮るすし屋はほとんどなくなっている。自家製を誇る店は間違いなくアタリである。
下野の国(栃木県)で栽培し、加工された干瓢は江戸の町に来て、巻きずしなどに欠かせないネタとなっている。
すし職人として最初に習うのも干瓢の仕込み方であるとも。
干瓢はぬるま湯で戻し、塩もみして水洗いする。これを砂糖、しょうゆで煮て、仕上げにみりんを振る。みりんを入れないという職人もいる。
今回のものは砂糖としょうゆ、少量の酒で煮て、仕上げに少量のみりんを振ったもの。やや甘味がちな味が巻きずしには合う。
近年、干瓢を煮るすし屋はほとんどなくなっている。自家製を誇る店は間違いなくアタリである。
寿司ネタ(made of)
スサビノリ
Nori
本種はもともとは東北地方や北海道の岩礁域の潮間帯に群生していた。・・・・
市場魚貝類図鑑で続きを読む⇒


 かんぴょう巻き鉄砲
かんぴょう巻き鉄砲 河童巻き
河童巻き 太巻きずし(千葉県君津市小櫃)
太巻きずし(千葉県君津市小櫃) 海苔(河童巻き)/スサビノリ
海苔(河童巻き)/スサビノリ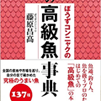 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典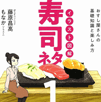 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生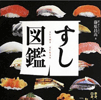 すし図鑑
すし図鑑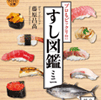 すし図鑑ミニ
すし図鑑ミニ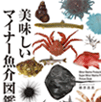 美味しいマイナー魚介図鑑
美味しいマイナー魚介図鑑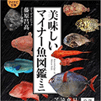 美味しいマイナー魚図鑑ミニ
美味しいマイナー魚図鑑ミニ ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー!
ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー! からだにおいしい魚の便利帳
からだにおいしい魚の便利帳 地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻
地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻