寿司図鑑 1326貫目
ハタハタずし
はたはたずし /


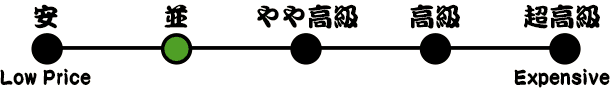
握り nigiri軍艦巻 gunkanmaki海苔巻 Norimaki丼・ちらし Don/Chirashi郷土ずし Kyoudozushiなれずし Narezushiいずし Izushiいなりずし Inarizushiその他 Others


それが山陰から北海道にかけては気温が低いので、単にご飯を合わせただけでは、乳酸発酵が進まず酸味やうま味が生まれなかった。それを補ったのが麹である。この麹を使った、「飯ずし」もすしの原型のひとつ。どちらが早いかというのではなく、別の系統だと思うべきだ。
塩をした魚介類に麹を加えて発酵させて、酸味よりもむしろうま味と甘味を醸し出した。サケ、ニシンなどでも作られているが、秋田県で作られているのが「ハタハタの飯ずし」である。古く秋田県では単に「すし」というと「ハタハタの飯ずし」のことだったという。
秋田県に一歩足を踏み入れるとスーパーでも魚屋さんでも普通に見かけるもので、秋田県人はこの穏やかな甘味が好きらしい。
写真は秋田県にかほ市『永田屋』のものであるが、小振りのハタハタをていねいに下ろして麹で漬け込んでいる。ニンジンやフクロフノリを彩りに見た目的にも秋田県のは「たはたずし」の中でも屈指の名品である。
寿司ネタ(made of)
ハタハタ
英名/japanese sandfish,Sailfin sandfish
古くは秋田県、山形県でとくに珍重していた。江戸時代から定置網、地引き網・・・・
市場魚貝類図鑑で続きを読む⇒


 ハタハタの酢じめ
ハタハタの酢じめ ハタハタ
ハタハタ ハタハタ酢締め
ハタハタ酢締め 白波多/ハタハタ
白波多/ハタハタ 白波多の握り
白波多の握り 白はたずし
白はたずし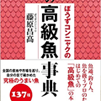 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典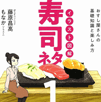 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生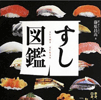 すし図鑑
すし図鑑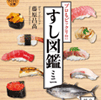 すし図鑑ミニ
すし図鑑ミニ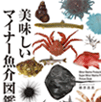 美味しいマイナー魚介図鑑
美味しいマイナー魚介図鑑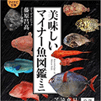 美味しいマイナー魚図鑑ミニ
美味しいマイナー魚図鑑ミニ ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー!
ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー! からだにおいしい魚の便利帳
からだにおいしい魚の便利帳 地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻
地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻