寿司図鑑 663貫目
寿司図鑑1~856貫目は旧コンテンツからの移行データの為、小さい写真の記事が多くあります。
寿司図鑑1~856貫目は旧コンテンツからの移行データの為、小さい写真の記事が多くあります。
清水さば
しみずさば /

腹の部分の握り。しっかり脂がある

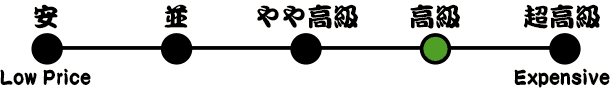
握り Nigiri軍艦巻 gunkanmaki海苔巻 Norimaki丼・ちらし Don/Chirashi郷土ずし Kyoudozushiなれずし Narezushiいずし Izushiいなりずし Inarizushiその他 Others
日本全国水産の世界で盛んなもの、それは魚貝類のブランド化である。
嚆矢はやはり大分県佐賀関の「関あじ」、「関さば」だろう。
それが最近では雨後の竹の子のごとく増えて、市場を歩くと、それこそたくさんの荷に意匠を凝らしたラベルがついている。
その中でも多いのがマアジとマサバである。
他にはアカムツ、ブリ、ホッケ、サケ、マダイにトリガイ、エゾイシカゲ、イワガキ。
産地が競い合うように、いろんなブランド名がついている。
高知県土佐清水市はマグロ、ソウダガツオ、ゴマサバ漁などで有名である。
これらの共通点は総て黒潮の恵みであることだ。
遠く関東で暮らしていると地図を見ただけで「黒潮洗う土佐清水」なんてイメージが浮かんでくるのだけど、いかがだろう。
さて、この土佐清水市で揚がるゴマサバのうまさは知る人ぞ知るものであった。
普通、ゴマサバは巻き網などで揚がるもの、それを土佐清水市では一本釣りしているのだ。
この独特の漁法で揚げたゴマサバを活け締めにして、出荷するのだけど、人呼んで「清水さば」という。
ブランド化に踏み切ったのは1994年であるが、別にブランド化のために新たに作り上げたものではない、というところがいい。
さて、この「清水さば」を手に入れるためには市場を歩いていても見つからない。
直接、土佐清水市の業者、もしくは土佐清水漁業協同組合にお願いするしかない。
今回のものも土佐清水漁業協同組合に「いいものが揚がったら送って下さい」と注文したもの。
 クリックで閉じます その連絡は突然やってきて、すぐ翌日夜には我が家に届いた。
クリックで閉じます その連絡は突然やってきて、すぐ翌日夜には我が家に届いた。
これを半日氷詰めのまま置き、翌朝押っ取り刀で『市場寿司 たか』まで持ち込む。
活け締めにした翌々日に荷物をあけたことになる。
そのゴマサバを手に持って、たかさんが大いに驚く。
「なんじゃ、これは! カチカチだね。こんなの初めてだよ」
大急ぎでおろしながらも、「包丁の感触がおかしいよ」と首をひねっているのだ。
確かにかたわらで見ていても「シコン」と包丁が入る。
「どーお、脂の乗り具合は」
「サバには思えない身質だけど、脂はあるようだね」
まずは刺身で食べてみる。
「これはうまいね。サバとは思えないね、でもカンパチやヒラマサでもないし」
「そうだね。イサキにも似ているし、カンパチにも似ているけど、初めて食べるって味だ」
困ったことに我らふたりとも、「清水さば」の味を的確に表現できない。
しかし、非常にうまいことは間違いなく、刺身で食べた余韻が舌に殷々と残っている。
背の部分。こちらはさっぱりとして、サバらしくない味わい
 クリックで閉じます 腹の部分と、背を分けて握りにする。
クリックで閉じます 腹の部分と、背を分けて握りにする。
「腹の方が脂があってうまいね。とても上品な脂だし」
「おれは背の方がいいや」
たかさんは比較的脂の少ない背がいいという。
「脂よりも食感に驚くね。シコっとしてる」
ふたりでなん個も口に放り込んで、まだまだ食べ飽きない、そんな実力を「清水さば」から見いだす。
ちなみにゴマサバがもっとも脂をつけるのは寒くなってだろう。
とすると、これはまだ“走り”なのだ。
「たかさん、これ寒の時期にどんな味がするんだろうね。ワクワクするね」
「するよ、その時期にも食べてみよう」
土佐清水市 清水さば
http://www.city.tosashimizu.kochi.jp/sight/shimizusaba/index.html
土佐清水漁業協同組合
高知県土佐清水市市場町11-4
電話0880-82-1221
嚆矢はやはり大分県佐賀関の「関あじ」、「関さば」だろう。
それが最近では雨後の竹の子のごとく増えて、市場を歩くと、それこそたくさんの荷に意匠を凝らしたラベルがついている。
その中でも多いのがマアジとマサバである。
他にはアカムツ、ブリ、ホッケ、サケ、マダイにトリガイ、エゾイシカゲ、イワガキ。
産地が競い合うように、いろんなブランド名がついている。
高知県土佐清水市はマグロ、ソウダガツオ、ゴマサバ漁などで有名である。
これらの共通点は総て黒潮の恵みであることだ。
遠く関東で暮らしていると地図を見ただけで「黒潮洗う土佐清水」なんてイメージが浮かんでくるのだけど、いかがだろう。
さて、この土佐清水市で揚がるゴマサバのうまさは知る人ぞ知るものであった。
普通、ゴマサバは巻き網などで揚がるもの、それを土佐清水市では一本釣りしているのだ。
この独特の漁法で揚げたゴマサバを活け締めにして、出荷するのだけど、人呼んで「清水さば」という。
ブランド化に踏み切ったのは1994年であるが、別にブランド化のために新たに作り上げたものではない、というところがいい。
さて、この「清水さば」を手に入れるためには市場を歩いていても見つからない。
直接、土佐清水市の業者、もしくは土佐清水漁業協同組合にお願いするしかない。
今回のものも土佐清水漁業協同組合に「いいものが揚がったら送って下さい」と注文したもの。


これを半日氷詰めのまま置き、翌朝押っ取り刀で『市場寿司 たか』まで持ち込む。
活け締めにした翌々日に荷物をあけたことになる。
そのゴマサバを手に持って、たかさんが大いに驚く。
「なんじゃ、これは! カチカチだね。こんなの初めてだよ」
大急ぎでおろしながらも、「包丁の感触がおかしいよ」と首をひねっているのだ。
確かにかたわらで見ていても「シコン」と包丁が入る。
「どーお、脂の乗り具合は」
「サバには思えない身質だけど、脂はあるようだね」
まずは刺身で食べてみる。
「これはうまいね。サバとは思えないね、でもカンパチやヒラマサでもないし」
「そうだね。イサキにも似ているし、カンパチにも似ているけど、初めて食べるって味だ」
困ったことに我らふたりとも、「清水さば」の味を的確に表現できない。
しかし、非常にうまいことは間違いなく、刺身で食べた余韻が舌に殷々と残っている。
背の部分。こちらはさっぱりとして、サバらしくない味わい


「腹の方が脂があってうまいね。とても上品な脂だし」
「おれは背の方がいいや」
たかさんは比較的脂の少ない背がいいという。
「脂よりも食感に驚くね。シコっとしてる」
ふたりでなん個も口に放り込んで、まだまだ食べ飽きない、そんな実力を「清水さば」から見いだす。
ちなみにゴマサバがもっとも脂をつけるのは寒くなってだろう。
とすると、これはまだ“走り”なのだ。
「たかさん、これ寒の時期にどんな味がするんだろうね。ワクワクするね」
「するよ、その時期にも食べてみよう」
土佐清水市 清水さば
http://www.city.tosashimizu.kochi.jp/sight/shimizusaba/index.html
土佐清水漁業協同組合
高知県土佐清水市市場町11-4
電話0880-82-1221
寿司ネタ(made of)
ゴマサバ
英名/blue mackerel 台湾/花腹鯖、芝麻鯖 中国/澳洲鯖
鮮魚としてより加工品原料としても重要なもの。節、干もの、総菜などに・・・・
市場魚貝類図鑑で続きを読む⇒


 首折さば握り
首折さば握り こけら寿司
こけら寿司 さば寿司
さば寿司 早なれずし
早なれずし さばのかぶらずし
さばのかぶらずし さば寿し
さば寿し 丸さば握り
丸さば握り 胡麻鯖握り
胡麻鯖握り 「酢にごし」を使った、ちらし寿司
「酢にごし」を使った、ちらし寿司 箱寿し
箱寿し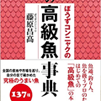 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典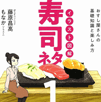 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生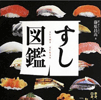 すし図鑑
すし図鑑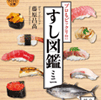 すし図鑑ミニ
すし図鑑ミニ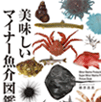 美味しいマイナー魚介図鑑
美味しいマイナー魚介図鑑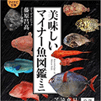 美味しいマイナー魚図鑑ミニ
美味しいマイナー魚図鑑ミニ ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー!
ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー! からだにおいしい魚の便利帳
からだにおいしい魚の便利帳 地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻
地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻