寿司図鑑 1309貫目
和歌山県有田市、さばなれずし
わかやまけんありたし、さばなれずし /


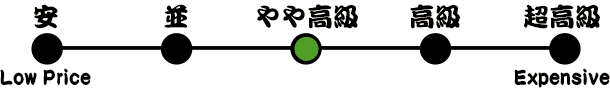
握り nigiri軍艦巻 gunkanmaki海苔巻 Norimaki丼・ちらし Don/Chirashi郷土ずし Kyoudozushiなれずし Narezushiいずし Izushiいなりずし Inarizushiその他 Others
有田市の一般家庭で作られた「さばなれずし」
すしの歴史は非常に古く稲作などとともに我が国に来たとされている。その最初のものが「なれずし」である。
塩をしたサバと炊いたご飯を合わせて、乳酸発酵させることで「酢し」、すなわち酸っぱくなったもの。
乳酸発酵がすすむと米はどろどろになり、粒が見えなくなってしまうほどで、ご飯を食べてもいいが、主役は魚である。
「なれずし」は乳酸菌の滅菌作用と、うま味・酸味を作り出すことで生まれる保存食である。
この酸味が古代の人々を魅了したのだろう。
和歌山県と三重県の旧紀州は滋賀県に次いでこの「なれずし」がよくみられる地である。
これは保存食としての「なれずし」を都(飛鳥、平城京)に供給していたためではないかと思っている。
ちなみに和歌山県には、ご飯が粥状になるまで発酵させ魚が主役の「本なれずし」があり、魚とご飯ともに食べる「生なれずし(半なれずし)」」があり、また発酵を伴わず、単に魚とすし飯を馴染ませるための、「早ずし」がある。
先にも述べたように、「なれずし」は基本的にご飯を食べるためのものではなく、魚(マサバ)を食べるためのものだが、和歌山県の「さばなれずし」はご飯も食べるし魚も食べるので「生なれずし」である。
この「さばなれずし」は和歌山市の高瀬有希子が送ってくれた、有田市のものだ。
一般家庭で作ったものだろうというのは、新聞の広告で巻かれていたところから想像しての、こちらの勝手な想像である。
和歌山県有田市のものも、和歌山市のものも、明らかに「生なれずし」である。
サバの切り身に塩をして数日寝かせ、塩抜きをする。
ご飯と合わせて、「あせ」の葉に巻いて桶に詰め、重しをして数日から1週間くらい寝かせる。
塩をしたサバと炊いたご飯を合わせて、乳酸発酵させることで「酢し」、すなわち酸っぱくなったもの。
乳酸発酵がすすむと米はどろどろになり、粒が見えなくなってしまうほどで、ご飯を食べてもいいが、主役は魚である。
「なれずし」は乳酸菌の滅菌作用と、うま味・酸味を作り出すことで生まれる保存食である。
この酸味が古代の人々を魅了したのだろう。
和歌山県と三重県の旧紀州は滋賀県に次いでこの「なれずし」がよくみられる地である。
これは保存食としての「なれずし」を都(飛鳥、平城京)に供給していたためではないかと思っている。
ちなみに和歌山県には、ご飯が粥状になるまで発酵させ魚が主役の「本なれずし」があり、魚とご飯ともに食べる「生なれずし(半なれずし)」」があり、また発酵を伴わず、単に魚とすし飯を馴染ませるための、「早ずし」がある。
先にも述べたように、「なれずし」は基本的にご飯を食べるためのものではなく、魚(マサバ)を食べるためのものだが、和歌山県の「さばなれずし」はご飯も食べるし魚も食べるので「生なれずし」である。
この「さばなれずし」は和歌山市の高瀬有希子が送ってくれた、有田市のものだ。
一般家庭で作ったものだろうというのは、新聞の広告で巻かれていたところから想像しての、こちらの勝手な想像である。
和歌山県有田市のものも、和歌山市のものも、明らかに「生なれずし」である。
サバの切り身に塩をして数日寝かせ、塩抜きをする。
ご飯と合わせて、「あせ」の葉に巻いて桶に詰め、重しをして数日から1週間くらい寝かせる。
保存性を高めるために「あせ」の葉で巻く


和歌山県の「なれずし」などで必ず使われているのが「あせ」と呼ばれているダンチクの葉である。
漢字は「暖竹」だが、竹ではなく、むしろ巨大なススキのようなものである。
この葉には殺菌力があるので、塩漬けにしたサバの切り身とご飯を包むと、腐敗しないで乳酸発酵が始まる。
発酵があまり進んでいないのでご飯粒はそのままだ
寿司ネタ(made of)
マサバ
Chub mackerel
古く都市部では大衆魚、下魚などとされ、安くてうまい魚の代名詞だった。鮮魚としても加工品と・・・・
市場魚貝類図鑑で続きを読む⇒



 しめさば握り
しめさば握り 寒さばの握り
寒さばの握り こけら寿司
こけら寿司 バッテラ
バッテラ さばのかぶらずし
さばのかぶらずし さば寿し
さば寿し 早ずし
早ずし 大根ずし
大根ずし ばらずし
ばらずし 早なれずし
早なれずし さばのかぶらずし
さばのかぶらずし さば寿し
さば寿し 富山県、城端別院善徳寺「鯖ずし」
富山県、城端別院善徳寺「鯖ずし」 さば松前寿し
さば松前寿し さば押し寿司
さば押し寿司 首折れさば
首折れさば 薬師神かまぼこの「鯖寿司」
薬師神かまぼこの「鯖寿司」 ばってら/マサバ
ばってら/マサバ 姫路『すし宗』、ばってら/マサバ
姫路『すし宗』、ばってら/マサバ 生鯖
生鯖 鯖寿司
鯖寿司 マサバ冷燻
マサバ冷燻 和歌山市弥助寿司の「さばなれずし」
和歌山市弥助寿司の「さばなれずし」 小さばの手こねずし
小さばの手こねずし 「酢にごし」を使った、ちらし寿司
「酢にごし」を使った、ちらし寿司 箱寿し
箱寿し 笹ずし
笹ずし 滋賀県日野、鯖なれずし
滋賀県日野、鯖なれずし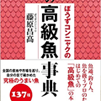 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典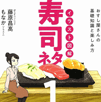 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生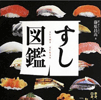 すし図鑑
すし図鑑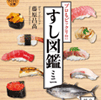 すし図鑑ミニ
すし図鑑ミニ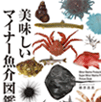 美味しいマイナー魚介図鑑
美味しいマイナー魚介図鑑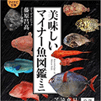 美味しいマイナー魚図鑑ミニ
美味しいマイナー魚図鑑ミニ ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー!
ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー! からだにおいしい魚の便利帳
からだにおいしい魚の便利帳 地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻
地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻