寿司図鑑 1433貫目
富山県、城端別院善徳寺「鯖ずし」
とやまけんじょうはなべついんぜんとくじさばずし /


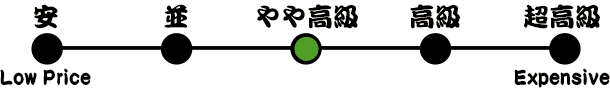
握り nigiri軍艦巻 gunkanmaki海苔巻 Norimaki丼・ちらし Don/Chirashi郷土ずし Kyoudozushiなれずし Narezushiいずし Izushiいなりずし Inarizushiその他 Others
砺波平野の奥にある寺と絹織物の町
城端は富山県の西の端、砺波平野のいちばん奥まったところにある。
町は真宗大谷派の大寺院である、城端別院善徳寺の門前町だ。
福井県から石川県、富山県にかけて浄土真宗の盛んなところで、その寺を中心に生まれた町でもある。
散居村で有名な平野に市街地を形成し、美しい建築物がそこかしこに見られえる。
大寺院なのに城端別院善徳寺は町の方達に愛されているのも素晴らしい。
5月には享保年間にまで歴史をたどれる豪華な城端曳山祭がある。
宗教的な地味な面と、華々しい、派手やかな面が共存してもいる。
国内でももっとも美しい町のひとつである。
富山県南砺市城端『真宗大谷派 城端別院 善徳寺』で7月22日から28日に行われるのが「虫干法会」である。
説話のあとの「お斎(おとき)」に出されるものが「鯖ずし」である。
町は真宗大谷派の大寺院である、城端別院善徳寺の門前町だ。
福井県から石川県、富山県にかけて浄土真宗の盛んなところで、その寺を中心に生まれた町でもある。
散居村で有名な平野に市街地を形成し、美しい建築物がそこかしこに見られえる。
大寺院なのに城端別院善徳寺は町の方達に愛されているのも素晴らしい。
5月には享保年間にまで歴史をたどれる豪華な城端曳山祭がある。
宗教的な地味な面と、華々しい、派手やかな面が共存してもいる。
国内でももっとも美しい町のひとつである。
富山県南砺市城端『真宗大谷派 城端別院 善徳寺』で7月22日から28日に行われるのが「虫干法会」である。
説話のあとの「お斎(おとき)」に出されるものが「鯖ずし」である。
麹を使ったすし地帯に長年造られ続けている、なれずし


福井県、富山県は漬け込みに麹を使った飯ずし(漬物ずし)地帯である。
寒冷な地域ではご飯と魚だけでは乳酸発酵が進まない。
それを麹が補っているのである。
実際、同南砺市井波には、こちらも大寺院である、井波別院瑞泉寺があり、夏の太子伝会のときに、「さばずし」が提供されている。
ただし、こちらはご飯と米麹が使われているなど、純粋な意味での「なれずし」ではなく、むしろ「飯ずし」とすべきだ。
また砺波平野にはサバだけではなく、ニシンなど様々な米麹を使った飯ずしが存在する。
そんななかなぜか真宗大谷派 城端別院 善徳寺だけが、炊いたご飯だけを使った「なれずし」が作られているのだろう。
さて、「鯖ずし」は5月に3日間ほどかけて塩漬け、塩抜きをして炊いたご飯と山椒の葉で漬け込む。
これを7月22日から28日に行われる「虫干法会」に振る舞われる。
広間に信者が並んで御斎を食べる
漬け込み期間が2ヶ月ほどと短い
寿司ネタ(made of)
マサバ
Chub mackerel
古く都市部では大衆魚、下魚などとされ、安くてうまい魚の代名詞だった。鮮魚としても加工品と・・・・
市場魚貝類図鑑で続きを読む⇒




 しめさば握り
しめさば握り 寒さばの握り
寒さばの握り こけら寿司
こけら寿司 バッテラ
バッテラ さばのかぶらずし
さばのかぶらずし さば寿し
さば寿し 早ずし
早ずし 大根ずし
大根ずし 和歌山県有田市、さばなれずし
和歌山県有田市、さばなれずし ばらずし
ばらずし 早なれずし
早なれずし さばのかぶらずし
さばのかぶらずし さば寿し
さば寿し さば松前寿し
さば松前寿し さば押し寿司
さば押し寿司 首折れさば
首折れさば 薬師神かまぼこの「鯖寿司」
薬師神かまぼこの「鯖寿司」 ばってら/マサバ
ばってら/マサバ 姫路『すし宗』、ばってら/マサバ
姫路『すし宗』、ばってら/マサバ 生鯖
生鯖 鯖寿司
鯖寿司 マサバ冷燻
マサバ冷燻 和歌山市弥助寿司の「さばなれずし」
和歌山市弥助寿司の「さばなれずし」 小さばの手こねずし
小さばの手こねずし 「酢にごし」を使った、ちらし寿司
「酢にごし」を使った、ちらし寿司 箱寿し
箱寿し 笹ずし
笹ずし 滋賀県日野、鯖なれずし
滋賀県日野、鯖なれずし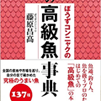 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典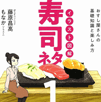 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生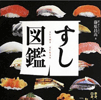 すし図鑑
すし図鑑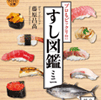 すし図鑑ミニ
すし図鑑ミニ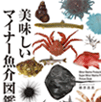 美味しいマイナー魚介図鑑
美味しいマイナー魚介図鑑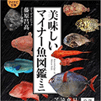 美味しいマイナー魚図鑑ミニ
美味しいマイナー魚図鑑ミニ ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー!
ぼうずコンニャクの全国47都道府県 うますぎゴーゴー! からだにおいしい魚の便利帳
からだにおいしい魚の便利帳 地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻
地域食材大百科〈第5巻〉魚介類、海藻